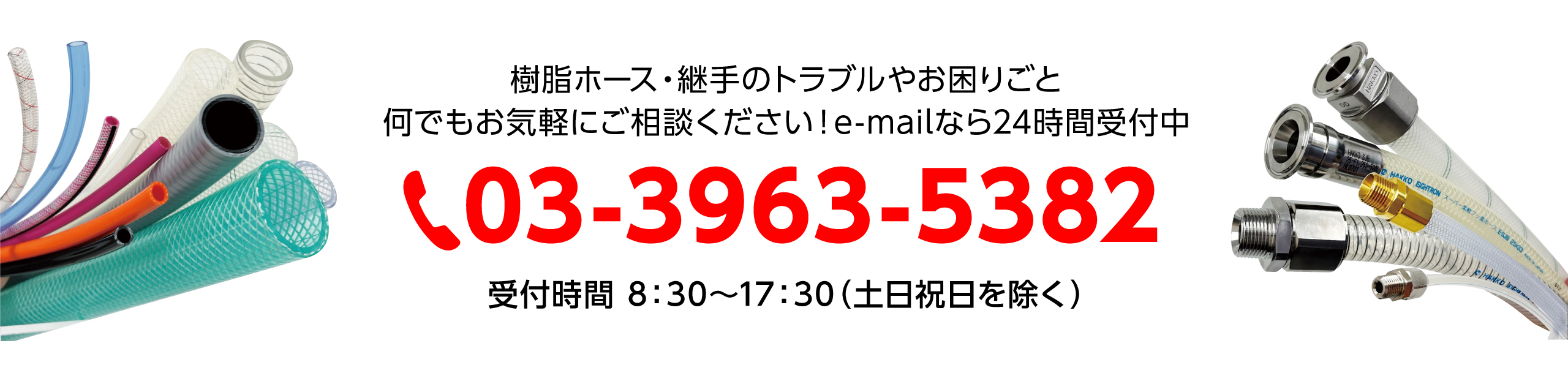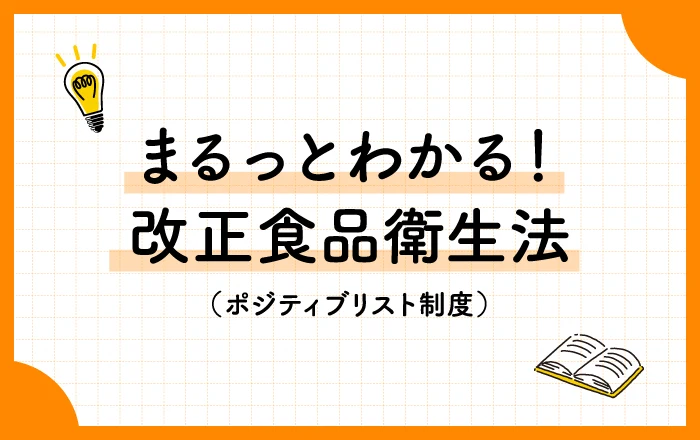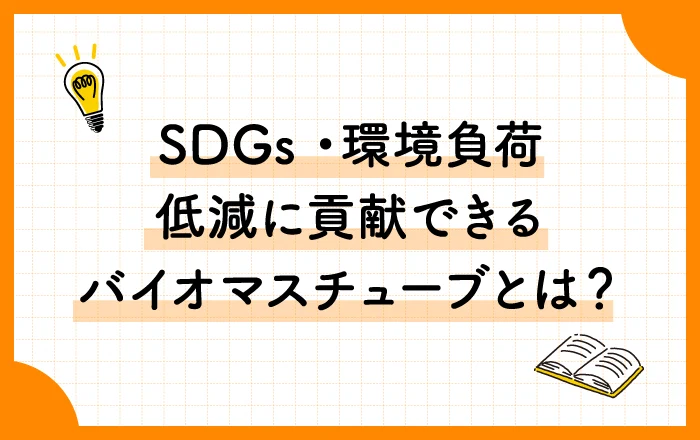データセンターの冷却水用途に適したホースは?

AI処理やクラウドインフラの急速な普及により、データセンターでは高密度なGPUサーバーや高性能機器の導入が進んでいます。その結果、計算性能の向上に伴って発熱量も増加しており、従来の空冷では対応が難しく、冷却効率の高い液冷への移行が加速しています。
液冷システムでは、冷却水を循環させるための配管が重要な役割を担います。とくに、ホースやチューブといった副資材は、冷却性能やシステム全体の信頼性に大きく関わっており、単なる消耗品ではなく、戦略的な部品として位置づける必要があります。
本記事では、データセンターで求められる冷却水用ホースの選定ポイントを、柔軟性・耐久性・接続性などの観点から整理します。液冷システムの設計・調達・保守に携わる技術担当者の方々にとって、適切な製品選定の参考となる内容をお届けします。
データセンターにおける冷却の重要性

近年、データセンターの冷却(チラー)設計には、より精緻な対応が求められています。単に発熱機器が増えただけでなく、電力密度の不均一性やホットスポットの発生、エネルギー効率の維持など、多くの課題が複雑に絡み合っています。
冷却性能の確保は、サーバー機器の安定稼働に直結するだけでなく、全体の運用コストやエネルギー効率、設備投資の最適化にも大きな影響を及ぼします。そのため、空調設備や冷却構造の刷新に加え、気流制御や副資材の選定なども含めた設計が求められます。
サーバー密度と高発熱化への対応
近年のAI活用やクラウド基盤の整備に伴い、1ラックあたりに搭載されるサーバー台数が増加し、電力密度は従来の5〜12kWから、AI対応ラックでは50〜100kWを超える水準に達しつつあります。
このような高密度化により、ラック内部やフロア全体で発熱が集中し、冷却(チラー)効率の低下やホットスポットの発生が深刻化しています。冷却が追いつかない場合、サーバーのパフォーマンス低下や機器の故障、運用停止リスクを招く可能性もあります。
主な対応策としては、ホットアイル・コールドアイルを明確に分離することによる気流制御の最適化、リアドアクーラーなどを活用した局所冷却、床下空間の気流設計の見直しなどが挙げられます。
また、CFD(数値流体力学)を用いた気流解析によって、冷却不足のエリアを可視化し、空調効率を事前にシミュレーションする手法も普及しています。
こうした取り組みは、熱的リスクの回避とともに、PUE(電力使用効率)の改善やエネルギーコストの最適化にも直結します。
空冷から液冷への移行背景とその影響
サーバー密度の増加によって発生する熱量が飛躍的に高まるなか、空冷のみでは十分な冷却が難しくなり、液冷方式の導入が急速に進んでいます。
液冷(ウォータークーリング)は、空気と比べて熱伝導率が数十倍高い冷却液(チラー)を用いることで、熱を効率よく除去できる仕組みです。とくにGPUやHPC(高性能計算機)などを多数搭載したサーバーにおいては、液冷が実質的な必須条件となりつつあります。
液冷移行の背景としては、以下のような要因が挙げられます。
- AI用途におけるGPU搭載機器の急増
- 高性能CPUによるラックあたりの発熱密度の上昇
- SDGsやZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)対応など省エネ要請の強化
- PUE最適化の観点から空調負荷の削減が求められている
- 海外ハイパースケーラー(Meta、Google、Microsoft等)による液冷導入事例の拡大
液冷方式には複数のアプローチがあり、リアドア水冷、コールドプレート冷却、液浸冷却などが用途に応じて使い分けられています。いずれも高発熱機器の安定稼働を支える有効な手段として、次世代データセンター設計の要となっています。
データセンターで用いられる冷却技術

近年、サーバーの高性能化とラック密度の上昇に伴い、従来の空冷方式だけでは冷却能力が追いつかない場面が増えています。これに対応するため、データセンターでは水や特殊液体を用いた「液冷」技術の導入が加速しています。液冷と一口に言っても、その方式は複数あり、冷却対象や設置環境、必要な設備条件によって最適な手法が異なります。
以下では、実用化が進んでいる代表的な3つの冷却方式について、冷却効率・導入コスト・メンテナンス性などの観点から比較します。
| 冷却方式 | 主な用途 | 主な用途・特徴 |
| リアドア水冷 | ・GPU搭載高発熱サーバー ・既存DCの液冷化 | ・ラック背面で冷却できる ・導入が比較的容易 |
| コールドプレート冷却(水冷ヒートシンク) | ・AI向けGPU・CPU ・HPC(スパコン) | ・直接チップを効率的に冷却 ・ラックごとの実装 |
| 液浸冷却 | ・超高密度システム ・静音・省スペースが求められる環境 | ・全体を液体に浸して冷却 ・冷却効率が非常に高い |
なお、こうした冷却方式を安全かつ安定して機能させるためには、冷却水を循環させるためのホースやチューブといった副資材の選定も重要な要素となります。
とくに液冷では、水漏れや熱負荷への対応力が求められるため、高い耐久性・難燃性・柔軟性を備えたホースの選定が冷却効率や保守性に直結します。
冷却水用ホースを選ぶ際の重要ポイント

液冷システムの性能や信頼性を最大限に引き出すためには、冷却水を循環させるホースやチューブといった副資材の品質も非常に重要です。
特にデータセンターやスーパーコンピュータ施設では、設置空間の制約や長時間の連続運用、高発熱環境下での安定性が求められるため、ホースの選定がシステム全体の冷却効率と保守性に直結します。
以下では、冷却システムに導入するホースを選定する際に重視すべき「3つのポイント」を解説します。
狭いスペースにも対応できる柔軟性
データセンター内の配管は、ラック背面や床下などスペースが限られており、複雑なルートを通す必要があります。こうした環境では、柔軟性に優れたホースを採用することで、最小曲げ半径を小さく抑えられ、設置やレイアウトの自由度が向上します。
柔軟なホースは、設置作業のしやすさや、保守時の脱着作業の効率化にも寄与するため、初期施工から長期的な運用管理に至るまで、多くのメリットをもたらします。
長期運用における耐久性とメンテナンス性
液冷システムは、年間を通じてほぼ連続的に稼働するため、ホースには耐熱性・耐圧性・耐薬品性といった高い耐久性能が求められます。使用環境によっては、フッ素樹脂や積層構造の強化素材を用いた製品が適しています。
また、保守作業のしやすさを考慮し、外装に識別ラインを設けたり、半透明構造を採用したりすることで、経年劣化や水漏れの兆候を早期に発見しやすくなります。長期使用に耐える素材を選ぶことは、冷却水(チラー水)漏れや突発的なトラブルの予防にもつながります。
接続時の漏れ防止と取り付けのしやすさ
冷却ホースの接続部は、漏れや圧力不良の原因となるリスクが高い箇所です。不適切な継手の選定や接続ミスにより、冷却性能の低下やシステム停止につながる恐れがあります。
信頼性の高い接続を実現するには、段付き形状や専用継手など、密封性に優れた構造の採用が有効です。また、施工現場での作業性にも配慮し、着脱しやすくミスを防止できる設計が求められます。
接続時の漏れ防止と取り付けのしやすさは、液冷システム全体の安定稼働に直結する重要なポイントです。
まとめ|データセンターの冷却水ホースは「柔軟性・耐熱性・難燃性」が選定のポイント
AIやクラウドサービスの拡大に伴い、データセンターの冷却ニーズはこれまで以上に高度化・多様化しています。液冷システムの導入が進む中で、冷却水を確実に循環させるためのホース類は、決して軽視できない重要な構成要素です。
狭い設置空間でも取り回しやすい柔軟性、長期運用に耐えうる耐久性、そして接続時の密封性と作業性。これらの条件を満たすホースを選定することで、冷却効率とメンテナンス性の両立が図れます。
特に、高発熱なAIデータセンターやスパコン施設では、難燃性や耐熱性を備えた高機能ホースが安定稼働の鍵となります。こうした要件に応える製品として、「柔軟フッ素ホースシリーズ」は優れた性能を発揮します。製品の詳細については、以下のページをご参照ください。
AIやクラウドサービスの拡大に伴い、データセンターの冷却ニーズはこれまで以上に高度化・多様化しています。液冷システムの導入が進む中で、冷却水を確実に循環させるためのホース類は、決して軽視できない重要な構成要素です。
狭い設置空間でも取り回しやすい柔軟性、長期運用に耐えうる耐久性、そして接続時の密封性と作業性。これらの条件を満たすホースを選定することで、冷却効率とメンテナンス性の両立が図れます。
「柔軟フッ素ホースシリーズ」は、こうした要件に対応したホースとして、AIデータセンターやスパコン施設における安定稼働を支える選択肢となります。製品の詳細については、以下のページをご参照ください。