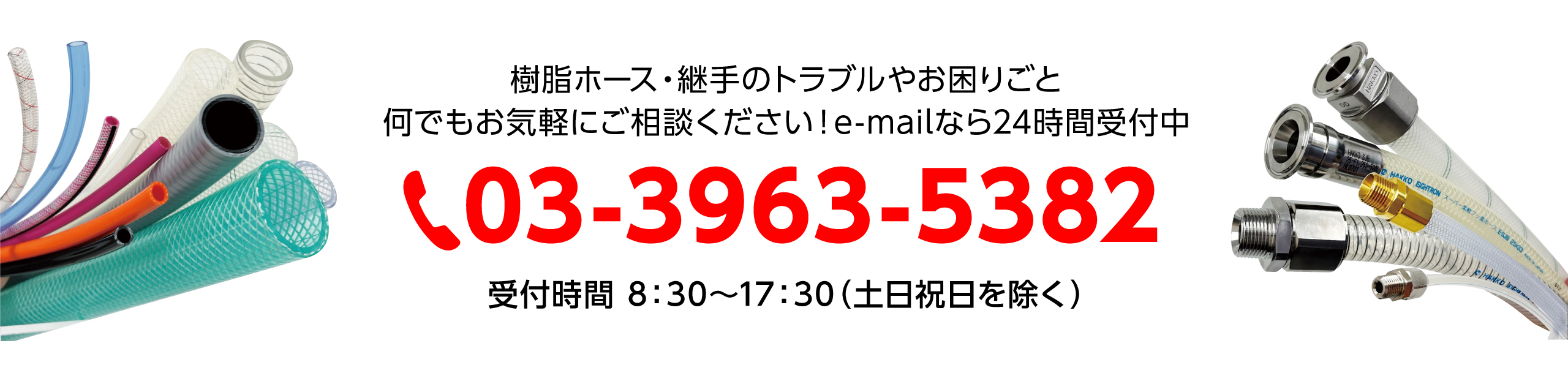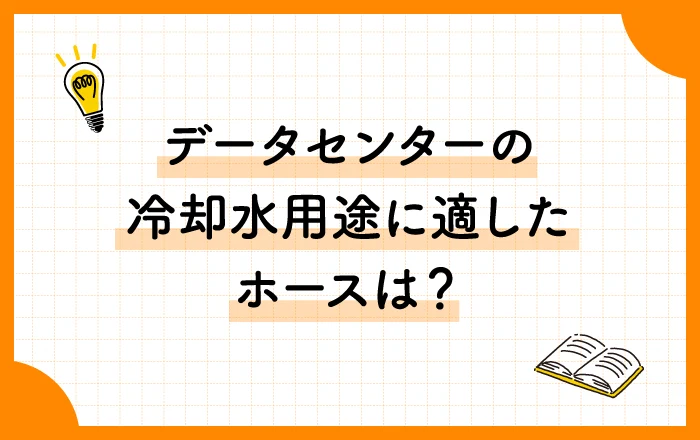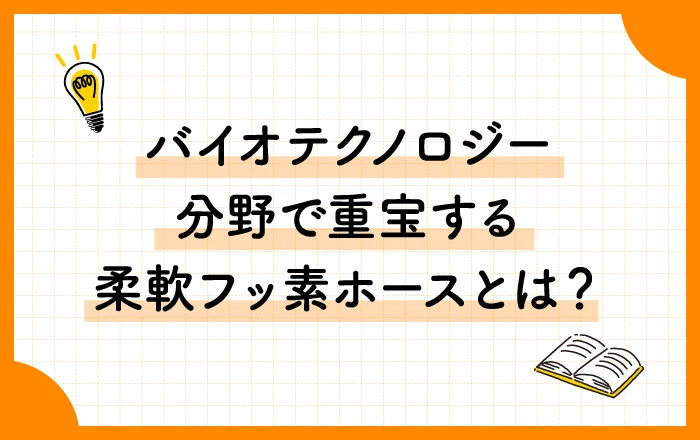SDGs・環境負荷低減に貢献できるバイオマスチューブとは?

製造現場で安心して使えることは、部品選定における第一条件です。しかし近年では、それに加えて「環境に配慮された素材かどうか」が求められる場面も増えています。
なかでもホースやチューブといった副資材は、これまで環境配慮といった観点では意識されにくかったといえます。
本記事では、植物由来の原料を使った“バイオマスチューブ”が、SDGsやスコープ3といった視点とどう関係しているのか、また従来品と比較して実用性に差があるのかを、設計・保全部門の目線でわかりやすく解説します。
バイオマスとは

「バイオマス」とは、動植物などの再生可能な有機資源のことを指します。語源は「bio(生物)+mass(質量)」で、石油や石炭などの化石資源とは異なり、比較的短期間で再生可能な炭素資源であることが特長
環境省ではバイオマスを「化石資源を除く、生物由来の有機性資源」と定義しています(※環境基本計画より)
| 分類 | 具体例 | 特徴 |
| 資源作物バイオマス | サトウキビ、トウモロコシ、木材、藁など | 資源としての利用を目的として栽培されたもの |
| 廃棄物系バイオマス | 廃棄物(生ごみ・建設発生木材)、家畜ふん尿など | 廃棄物として発生しているもの |
| 未利用バイオマス | 稲わら、麦わら、もみ殻など | 資源として利用されずに廃棄されているもの |
バイオマスは、再生可能な炭素資源として、環境負荷の低減や石油資源への依存回避の観点から、企業活動や製品選定において重要なキーワードとなっています。
カーボンニュートラルの実現が世界的な目標とされるなか、原材料や副資材にも環境配慮が求められています。こうした流れを受けて、近年ではチューブやホースといった工業製品にも、バイオマス由来の素材を取り入れる動きが広がっています。
こうした製品を適切に評価・選定するためには、導入のメリットや技術的要件を検討する前に、「バイオマスとはそもそも何か」という基本的な理解が欠かせません。
バイオマスチューブがSDGsに貢献できる理由
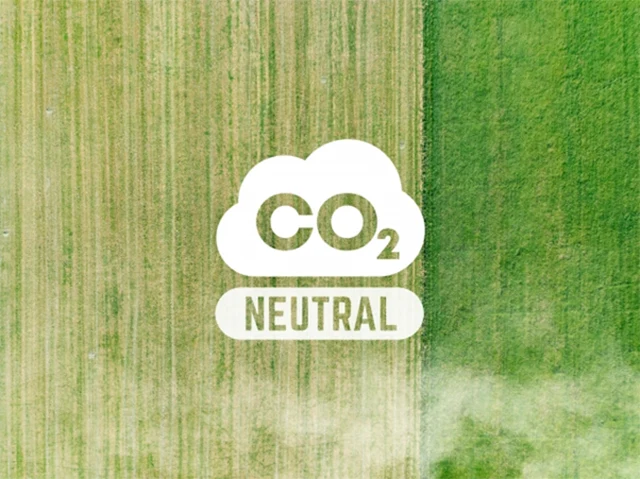
環境負荷の低減と資源循環の実現は、企業活動においても重要なテーマとなっています。特に製品の原材料や製造プロセスが地球環境へ与える影響は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に直結する課題です。
バイオマスチューブは、石油由来の素材に代わり植物由来の樹脂を一部に使用した製品で、資源の持続可能な利用と温室効果ガスの削減に貢献する素材です。
以下では、バイオマスチューブがなぜ環境にやさしく、SDGsに貢献する製品といえるのかを、「カーボンニュートラル」と「ライフサイクル」の観点から解説します。
カーボンニュートラルの実現
バイオマス原料には、サトウキビやトウモロコシといった植物性の資源が使われます。これらの植物は、成長過程で大気中のCO₂を吸収するため、原料として使用した後に焼却しても、理論上は大気中のCO₂を増加させないと考えられています。これが「カーボンニュートラル」という考え方です。
たとえば、植物由来のポリエチレンやポリプロピレンなどは、石油を原料とした同等製品に比べて、製造段階での温室効果ガス排出量(スコープ3・カテゴリ1)を削減できる可能性があります。
ただし、こうした効果を数値で裏付けるには、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的なCO₂排出量の算出が不可欠です。
ライフサイクルと環境負荷の低減
LCAとは、製品の「原料調達・製造・使用・廃棄」までを一連の流れとし、それぞれの段階で発生する環境負荷を定量的に評価する手法です。バイオマスチューブのような素材選定では、LCAを通じて温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の削減効果を可視化することができます。
また、廃棄時における特性もバイオマス素材の利点のひとつです。植物由来の樹脂は焼却しても、成長過程で吸収したCO₂と排出量が相殺されるため、排出量を実質ゼロと見なすことが可能です。
一方で注意すべき点として、「バイオマス=生分解性」とは限りません。すべてのバイオマス素材が自然環境で分解されるわけではなく、用途に応じて生分解性素材と非分解性素材が使い分けられています。
副資材も“評価対象”に。素材選定がSDGs実践に与える影響

製品の環境対応が求められるなかで、本体構造や主要素材に意識が向くのは自然な流れです。しかし、ホースやチューブのような副資材にも素材選定の責任があり、これらの選択が企業のSDGs実践度に直結します。
以下では、調達・製造部門が直面する脱炭素対応の現実と、それに適応するための素材選定の考え方を解説します。
調達・製造現場が求められる温室効果ガスの削減
GHG(温室効果ガス)排出量の削減は、持続可能な事業活動を行う上で避けて通れないテーマだといえます。
企業が排出するGHGは、以下のスコープ1〜3に分類されます。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
| スコープ1 | 自社で直接排出する温室効果ガス | ボイラーや社用車の燃料燃焼、工場の排出ガスなど |
| スコープ2 | 他社が排出したが自社の活動に伴う間接排出(エネルギー起因) | 購入した電力や蒸気の使用による排出 |
| スコープ3 | サプライチェーン全体で発生する間接排出 | 原材料の調達、製品の輸送、廃棄、通勤など |
なかでも、スコープ3カテゴリ1(購入品・サービス由来排出)は、製造業のGHG排出全体の70%以上を占めることもあるとされており、調達段階の素材選定が重要な削減ポイントとなります。
バイオマス素材は植物由来の原料を用いることで、スコープ3の排出削減に直結し、脱炭素経営を実践するうえで有効な選択肢になります。
副資材にも求められる「環境配慮型素材」の考え方
これまでの環境対応では、製品の主要構成部品や原料に注目が集まりがちでした。しかし近年では、ホースやチューブといった副資材も、環境負荷評価の対象とされるようになっています。
環境配慮型素材とは、主に以下のような特徴を備えた材料を指します。
- 再生可能な資源(例:植物由来樹脂)を使用している
- 製造時の温室効果ガス排出量が少ない
- 焼却時にカーボンニュートラルとみなされる
- 第三者機関の認証を取得している
副資材にまで環境配慮が及んでいるかどうかは、企業としてのサステナビリティ姿勢を問う評価指標になりつつあります。特に環境報告書や調達基準での対応が求められるケースでは、バイオマス素材の採用が対応手段のひとつだといえます。
調達先や顧客から「環境配慮型素材の使用実績」を問われた際に、認証や数値データを持って説明できるかどうかが、企業間取引や新規案件の獲得においても差を生む時代になりつつあります。
バイオマスホースは“環境”と“実用性”を両立できるのか?

バイオマスホースの評価では、「環境配慮」と「実用性」の両立が重要な基準となります。
近年では、柔軟性や耐圧性といった基本性能が石油由来のホースと同等に確保されており、加工性や成形性にも優れているため、既存の配管設計や継手をそのまま活用できるケースも少なくありません。
一例として、八興のスーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)【E-SJECO】をご紹介いたします。
「スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)【E-SJECO】」は、外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用することで、従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減したフッ素積層チューブです。
価格はやや高めですが、環境配慮型製品としての加点評価や調達上のメリットにより、導入が検討される場面が増えています。
素材の改良も進み、長期的な耐久性や安定性も十分に実用水準を満たすようになってきました。
環境対応と機能性を兼ね備えた選択肢として、バイオマスホースは今後ますます注目される存在になるといえます。
まとめ|環境負荷低減に貢献するバイオマスホースでSDGs対策を
脱炭素経営やスコープ3対応に取り組む企業にとって、副資材の素材選定も重要なテーマです。
スコープ3への対応や脱炭素経営の推進が求められるなか、副資材レベルでの素材選定にも環境配慮が求められています。
バイオマス素材を使用したチューブ・ホースは、製造時のCO₂排出を抑えられるだけでなく、LCAやバイオマスマーク認証といった裏付けにより、SDGsの方針に沿った調達活動にも活用できる点が特長です。
さらに、柔軟性・加工性・耐久性などの基本性能も従来製品と遜色なく、現場での使用にも十分対応可能です。
「環境に配慮した部材を使いたいが、実用性も妥協したくない」その両立を実現する選択肢として、バイオマスホースを使用する企業様も少なくありません。
製品仕様・導入事例・環境評価データなど、貴社の選定基準に即した情報をご提供しております。まずはお気軽にご相談ください。