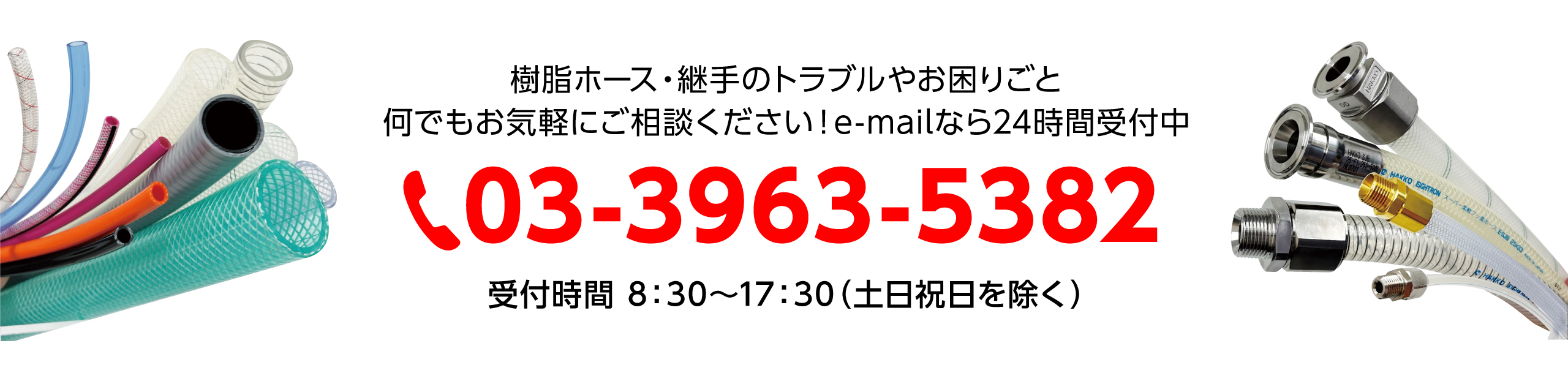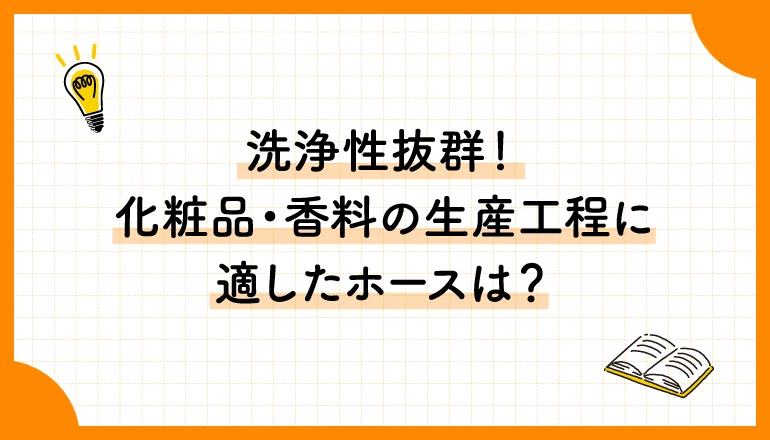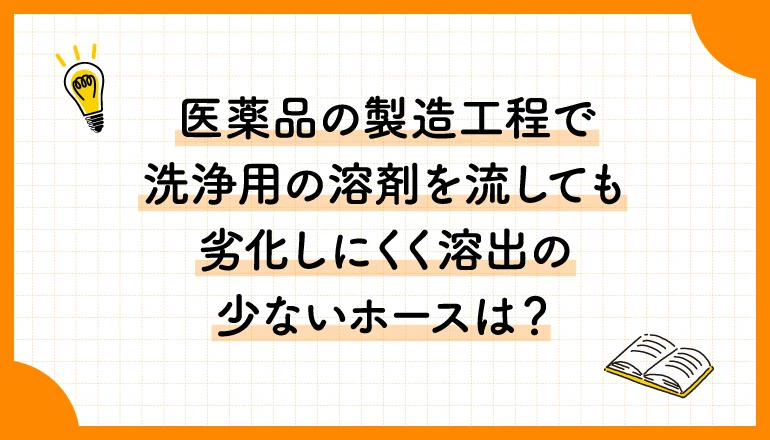ケトン類・アミン類を流せるスーパーホースは?
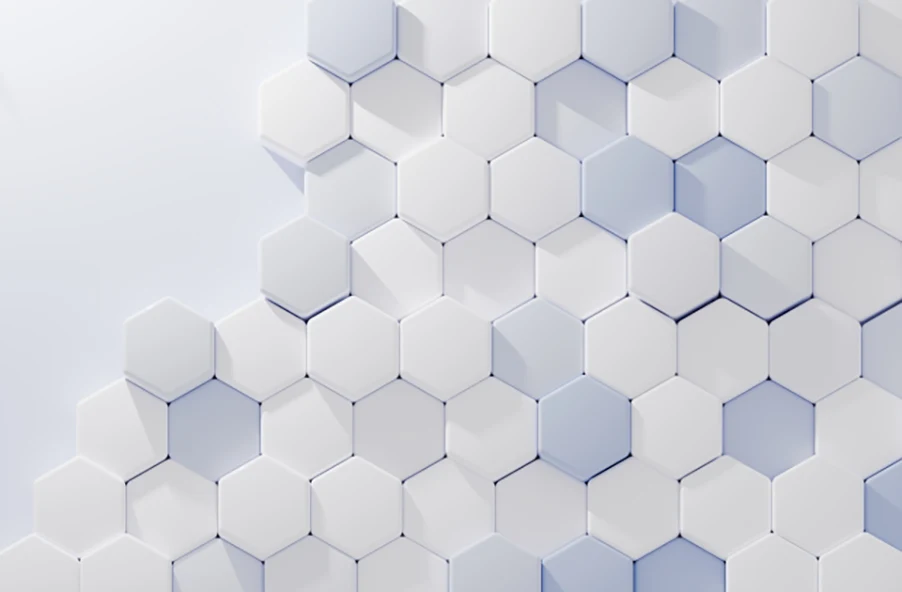
塗料やインク、接着剤、洗浄液といった多種多様な有機溶剤を使用する製造現場では、ホースの選定が製品の品質、生産効率、そして作業の安全性を大きく左右します。
なかでもケトン類(アセトン、MEKなど)は非常に極性が高く、強い溶解力を持つ有機溶剤です。また、アミン類も有機溶剤としてよく使用される薬品の一つです。
一般的な塩ビ(PVC)やゴム製のホースでは、膨潤やひび割れ、硬化といった劣化を引き起こします。こうした劣化は配管の破損や液漏れ、臭気トラブルといった大きなリスクにつながりかねません。
本記事では、一般的なホースがなぜ有機溶剤やアミン類、特にケトン類に対応できないのかという原因を解説し、耐薬品性に優れたホース選定のポイントをご紹介します。さらに、八興の「スーパー柔軟フッ素ホース」シリーズの特長と実際の導入事例を通じて、有機溶剤を扱う現場の課題解決策をご提案いたします。
有機溶剤に適したホースを選ぶ際に注意すべきこととは?
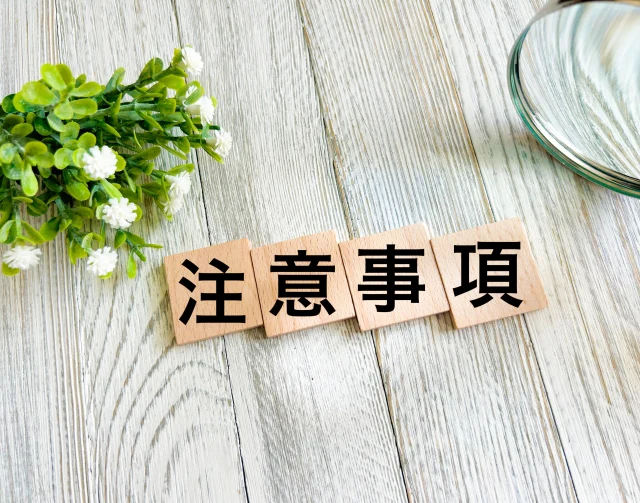
有機溶剤を扱う現場では、ホースの選定を誤ると膨潤やひび割れによる液漏れ、静電気の火花による引火リスク、さらには作業効率の低下といった重大なトラブルに発展しかねません。
特に、アセトンやMEKなどのケトン類は強い溶解力を持つため、一般的なゴムや塩ビ製のホースでは対応できない場合があります。
ここでは、有機溶剤対応ホースを選定する際に押さえておきたい「耐溶剤性」「帯電防止性」「柔軟性」の3つの観点から、それぞれの注意点を詳しくみていきましょう。
耐溶剤性|膨潤や劣化を防ぐために必要な素材選定
有機溶剤の強い溶解力は、ホース内部の素材に直接ダメージを与えます。特にケトン類やエステル類、芳香族炭化水素は、PVC(塩ビ)やNBR(ニトリルゴム)などの一般的な素材では短期間で膨潤・ひび割れ・硬化などの劣化を引き起こすことがあります。
そのため、ホース選定時には使用する溶剤の種類や濃度に応じて、PTFE(フッ素樹脂)やETFE、PFAなどの耐溶剤性に優れた素材を選ぶことが重要です。こうした素材は化学的に安定しており、多くの有機溶剤に対して長期間の使用が可能です。
さらに、メーカーが公開している「耐薬品表」や「適合リスト」を活用し、使用する溶剤とホースの相性を事前に確認することがトラブル防止につながります。
耐薬品性能について知りたい方は、以下のページをご確認ください。
https://eightron.tokyo/data/
帯電防止性|可燃性溶剤でも安全な静電気対策
有機溶剤の多くは引火性を持っており、移送中に発生する静電気によるスパークが火災の原因になることがあります。特に高速での液体移送や乾燥した環境では、ホース内部での帯電が起こりやすくなります。
このリスクを回避するためには、導電性素材を使用したホースや、帯電防止処理が施された構造のものを選定することが不可欠です。ホースによっては内部にアース線が埋め込まれており、しっかりと接地することで安全性が確保できます。
詳しくは後で紹介する「帯電防止ホースを取り扱う上での注意点」でご確認ください。
柔軟性|取り回しやすさで作業効率アップ
耐薬品性や帯電防止性に優れたホースの中には、素材特性上どうしても硬く、配管が難しいものも存在します。現場では限られたスペースでの施工や、頻繁な脱着・洗浄といった作業が求められることも多いため、ホースの柔軟性や取り回しやすさも重要な選定基準となります。
近年では、PTFEライニング+柔軟外被といった多層構造によって、耐薬品性と柔軟性を両立したホースも登場しています。また、最小曲げ半径や屈曲疲労性能なども、選定時に確認しておくと安心です。
ホースが硬すぎて無理な力がかかると、継手部の緩みや破断といった事故にもつながりかねません。安全性だけでなく、日々の作業効率や保守性の観点からも柔軟性の確認は欠かせないポイントです。
帯電防止ホースを取り扱う上での注意点
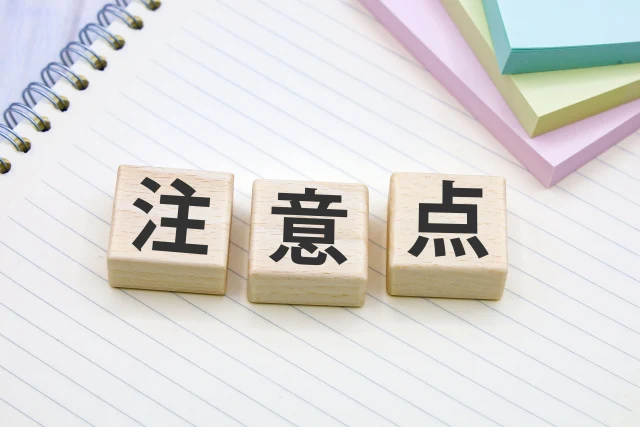
有機溶剤の多くは引火性を有しており、移送中に発生する静電気による火花放電が火災や爆発につながるリスクがあります。このため、溶剤搬送用ホースには帯電防止性能が求められ、あわせて適切な接地(アース)対策も講じる必要があります。
とくに、静電気の発生リスクが高まるのは、可燃性流体を高速で移送する場合や、フィルターを通して流す場面、または乾燥した冬場の環境などです。こうした条件下では、ホース内に発生した静電気が放電し、溶剤の引火点を超えると発火する危険性があります。
こうしたリスクを回避するために推奨されるのが、導電性構造を採用したホースの使用です。一般的な帯電防止ホースは部分的な導電層や導電ラインを用いていますが、それだけではホース表面や全体の電荷を確実に逃がすことができず、静電気が蓄積してしまう可能性があります。
以下のホースは、内層全体が導電性フッ素樹脂(ETFE)で構成されており、ホース全体で電荷を拡散・放出する構造になっています。また、IEC/TS 60079-32-1:2013(爆発性雰囲気 パート32-1:静電気の危険のためのガイドライン)に準拠しており、引火性液体を扱う現場での使用に最適です。
● 導電スーパー柔軟フッ素スプリング【E-SJSD】
● 導電スーパー柔軟フッ素チューブ【E-SJD】
なお、これらのホースを安全に使用するためには、ホース両端の金属継手を介して確実な接地処理(アース)を行うことが前提となります。静電気の発生は製品選定だけでなく、運用方法にも大きく左右されるため、現場ごとの条件に応じた管理が求められます。
導電抵抗値や各種試験成績書、RoHS2・UL規格対応などの技術資料も整備されており、安全面・信頼性の面でも安心して導入できます。
引火性溶剤を扱う現場では、こうした帯電防止+接地対応済みのホース選定と正しい運用管理の両立が不可欠です。詳細は以下の公式ページをご参照ください。
引火性流体用ホースの静電気対策について
ホース保管上の注意点

ホースの性能を長く保ち、安全に使用するためには、保管時の取り扱いが非常に重要です。とくに溶剤や帯電防止対応などの高機能ホースは保管状態が悪い場合、変形するなどのトラブルの原因になることもあります。
ホースを保管する際は、以下の3点を意識してしてください。
- 直射日光・湿気を避け、冷暗所で保管する
ホースは直射日光や雨風、高湿度にさらされると、硬化・変色・カビの発生などが起こりやすくなります。
保管は、風通しがよく湿度の低い冷暗所が最適です。温度変化や結露の多い場所も避けましょう。
- ねじれ・折れ・過度な曲げを取り除いて保管する
保管前には、ホースに残ったねじれや折れをしっかり解消してください。極端に曲げた状態や凹凸のある面での保管は、変形や層剥離、ひび割れの原因になります。
可能であれば、平らで滑らかな場所に、緩やかに伸ばした状態で保管するのが理想です。
- 異物混入・接触物に注意する
ホース内にゴミや異物が入ると、詰まりや機器トラブルの原因になります。保管時はキャップなどで口を塞ぎ、清潔に保つことが大切です。また、ゴムホースやゴム板と直接触れると可塑剤などの成分が移行し、変色や臭気の原因になるため、材質の異なる製品とは離して保管してください。
この3つのポイントを守るだけでも、ホースの耐久性・安全性・作業時の信頼性を大きく高めることができます。使用していないときこそ、適切な保管で製品を守る意識を持ちましょう。
まとめ|有機溶剤を送液するホースは「耐薬品性」を確認すること
有機溶剤を扱う製造現場では、ホース選定のミスが製品の不良、設備トラブル、さらには作業者の安全リスクに直結します。特にアセトンやMEKなどのケトン類は溶解力が非常に高く、一般的なホース素材では膨潤やひび割れが発生しやすいため注意が必要です。
ホース選定時にはまず、使用する溶剤との相性(耐薬品性)を第一に確認し、そのうえで以下の観点も考慮しましょう。
項目 確認内容/ポイント
帯電防止性能 静電気による引火リスクを防ぐため、導電構造やアース接続の可否を確認する
柔軟性・取り回し性 配管や脱着作業が多い現場では、最小曲げ半径やホースのしなやかさが重要
保管方法 直射日光・高湿・ねじれを避け、冷暗所での清潔な保管環境を整える
特に、「導電スーパー柔軟フッ素ホース」シリーズ(E-SJD/E-SJSD)のように、耐溶剤性・導電性・柔軟性を高いレベルで兼ね備えた製品を選ぶことで、溶剤移送の信頼性と安全性を大きく向上させることができます。
製造工程の安定と作業者の安全を守るためにも、「とりあえず使えるホース」ではなく、現場の用途に適したホースを“根拠を持って”選定することが非常に重要です。
使用前・保管中・導入後の各フェーズで、必要な対策をしっかり押さえておきましょう。
有機溶剤の種類と樹脂の耐薬品性をお調べになりたい方は、以下のリンクよりご確認ください。
https://eightron.tokyo/flux/